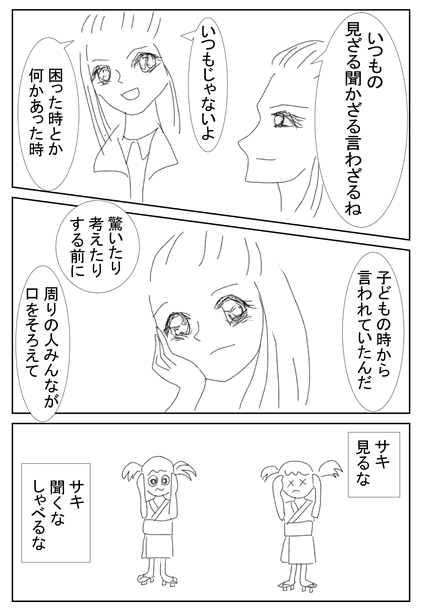ハンスは燭台を手に暗い廊下を進んだ。奥の壁に掛けられた絵の前で立ち止るとうつむいた。これまでこの絵をちゃんと見たことがなかった。ハンスは意を決して顔を上げた。「ああっ」描かれている女性はハンスの祖母だった。祖母はハンスが小さい頃に亡くなった。ハンスがいたずらをする度にいつもかばってくれた祖母だった。その祖母が若く美しい姿で絵の中にいた。祖母がハンスを見て笑ったような気がした。ハンスはすぐに目をそむけた。目が合うと絵の中に吸い込まれる。幼い頃から聞かされた言い伝えがハンスの頭に叩き込まれていた。
トーラとサトウ
トーラとサトウは隠し部屋へと向かった。サトウはトーラに請われてまたここまで来たが、もうこれ以上トーラに振り回されたくない、これを最後に別れを告げよう、内心そう決意していた。
廊下を進むとサトウは立ち止まった。
「絵がない」
「えっ」
トーラも壁を見た。前に来たときは確かに掛けられていた絵が、まるでたった今、誰かに持ち去られたかのようになくなっていた。
「いったい誰が」
「お父様かペーターかしら。ここに来たことがばれたのかも」
二人は顔を見合わせて佇んだ。
「行きましょう。考えていたって仕方ない」
トーラに促されてサトウは隠し部屋の扉を開けた。
トーラとサトウは奥へと進んだ。床に置かれた棺の前に来るとトーラは首を傾げた。
「サトウ、この棺の蓋、閉めたかしら」
「どうだったろう。閉めずにあわてて逃げた気がする」
「棺を開けてみましょう」
トーラに促され、サトウは重い蓋をずらして床に置いた。
「ああっ」
「いない」
棺はもぬけの殻だった。前に来た時には横たわっていた死体が消えていた。
二人はしばらく空の棺を見つめていたが、やがてサトウは重い蓋を棺に戻した。
サトウは心を決めた。もうベルリンへ戻ろう。これ以上この城にいることはできない。
トーラとハンス
ハンスは誰もいないのを見計らって、地下室へ続く階段を降りた。
一番奥の倉庫の前まで来ると、手にしていた鍵を取りだした。大きくて古い鍵だった。錠前に挿すと鍵はぴったりと収まった。ハンスは鍵を回した。
しかし鍵は開かなかった。解錠できなかった。
「何をしているの」
鍵と格闘していたハンスはギョッとして顔をあげた。
「トーラ、どうしてここに」
ハンスは逃げ出そうと地下室の通路を駈け出した。しかし、トーラとサトウに行く手を阻まれて階段の手前で座り込んだ。
「手にしているものを見せなさい」
「いやだ」
「サトウ、ハンスが持っているものを取り上げて」
しかしサトウは動かなかった。
「トーラ、ハンスの話を聞いてみよう」
「サトウ、私に逆らうつもり?」
「ハンス、何があったんだ」
「サトウ、ぼくの味方になって」
「僕は君の敵じゃないよ」

三人は東棟の奥の客間へ移った。
ソファに座ったハンスを囲い込むようにして両脇にトーラとサトウが腰かけた。
「さあ、持っているものを見せて」
ハンスはトーラの前に両手を出した。その手に握られていたのは、古びて鈍い光を放っている鍵、黄金でできた鍵だった。
「これは、この鍵は」
トーラは鍵を受取るとしげしげと眺めた。
「どうやって手に入れたの?」
「お母様が僕のところにやってきて僕にくれたんだ」
「お母様って、あの棺に入っていた?」
「そうだよ。棺から起きだして僕の部屋まで歩いてきたんだ」
サトウは背筋が凍った。トーラも顔をこわばらせた。
「棺の蓋が開いたから、自分で出て歩いてきたんだって」
「本当に、お母様だったの?」
「そうだよ。間違えるわけないじゃん」
「お母様がこの鍵を渡してくれたの?」
「うん、それから廊下の絵を取ってきてほしいって」
「お母様の頼みだから、廊下から絵を取ってきて地下室へも行ったのね。あんなに恐がりのくせに」
「お母様は暗い所しか歩けないって言っていた。それにたくさん歩けないって」
「ハンス、あなた恐くないの?」
「だってお母様だよ。恐いわけないよ」
「あなたのその能天気なところ、今回は役に立ったわ」
「なんだよ。役に立つもなにも、トーラには関係ないよ。ぼくとお母様の約束なんだから」
「棺の蓋を閉めたのも君なのか?」
「うん、お母様がまた棺で眠ってしまわないよう蓋をしたんだ」
「ハンス、お母様はあの絵と地下室の秘薬をどうするつもりなの?」
「知らない」
ハンスは顔をそむけた。
「言いたくないならいいのよ。この鍵、この黄金の鍵があれば何でも手に入る」
トーラは掌にのせた鍵を愛おしそうに撫でた。
「ハンス。あなたも知っているでしょう。うちの家宝。錠前術のマイスターだけが使える万能の鍵がある、それは黄金でできている」
「お母様は僕に鍵を渡すって。僕が受け継ぐんだって」
「いいえ、あなたは受け継げない。解錠できなかったのなら、あなたはマイスターではないのよ」
「そんなことない。僕、錠前術はマスターしている」
「でも鍵は開けられなかった」
「マイスターになるのは僕だよ。もう一度やってみる」
ハンスはトーラの手から鍵を奪おうとしたがトーラは渡さなかった。
「私がやる」
「できるわけない。鍵に関しては、僕のほうがトーラより何倍も優秀なんだから」
「それは鍵を使ってみればわかることだわ」
トーラは黄金の鍵を胸元に仕舞い込んだ。
「ねえ、返してくれよ。お母様は僕にくれたんだから」
「地下室へ行くわよ。ハンス、ついてらっしゃい」
「トーラの思い通りになんかならないよ」
ハンスはするりとソファから滑りおり、軽い身のこなしで部屋を飛び出していった。

トーラはサトウを従えて地下室の階段を下りた。奥の扉の前まで来ると、手にしていた黄金の鍵を鍵穴へ差し込んだ。
鍵は開かなかった。
トーラは鍵を引き抜いて差し直したり回したりしたが解錠できなかった。
「そんなはずないわ。ハンスが無理なら、私が、できるはず」
「僕がやってみようか」
「ばかなこと言わないで。サトウにできるはずないでしょう」
トーラの剣幕に押されてサトウは伸ばしかけた手を引っ込めた。
「私かハンス、どちらかが開けなかったら、この家の伝統は途絶えてしまう。開けられないなんて、有りえない」
トーラはもう一度、鍵穴に鍵を差し込んだ。
「まさか、これ、マスターキーではないのかしら」
「いいえ、それは、紛れもなく、黄金の、マスターキーです」
背後からの声にトーラとサトウはぎょっとした。
「お母様!」
「あなたに、鍵は、開けられない」
暗い地下室の廊下に、ギヨン夫人とハンスが立っていた。