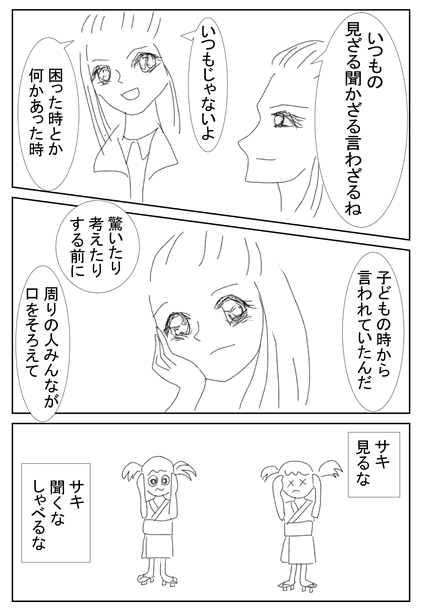盆が近くなり、サキは本所の実家へ帰省することにした。実家から学校までさほど遠くはなかったが、ほとんどの生徒は寄宿舎に入るのでサキも寄宿舎へ入舎していた。
盆休み
「今年はお盆、どうするの」
フミがサキとメグミに訊いた。
「私は金曜に帰る。メグミさんは?」
「私はまだ決めていない。週明けに帰ろうかしら」
実家が横浜にあるメグミは、気が向いた時に家の車を呼んで、気軽に行き来することがよくあった。
「フミさんはどうするの」
「今年は帰らないつもり。6月に法事で帰省したばかりだから」
「お父様やお母様はがっかりするでしょうね」
フミは力なく笑った。今年、寄宿舎に残るのは不安だった。何故か落ち着かない。でも今更、帰り支度をするのは大変だ。実家が遠いフミにとって帰省は大ごとだった。実家に連絡してお金を送金してもらわなければいけないし、汽車の切符や車の手配をして、学校にも外泊届を提出しなくちゃいけない。
「そうそう、今年の夏休みは山本先生が寄宿舎の監督をするそうよ」
「えー、山本先生!うるさく監督されそうだな。目をつけられたらどうしよう」
口うるさい山本先生は苦手だったが、人の少なくなるお盆の時期に、山本先生がいてくれるのは心強かった。フミはすこし安心した。
帰省
「それじゃ、メグミさん、フミさん。行ってまいります」
「気をつけてね。9月の新学期に会いましょう」
挨拶をかわしてサキを校門から送り出すと、メグミとフミは寄宿舎の庭をゆっくり散歩した。
「フミさん、このごろ変よ」
「えっ」
「なんだかいつも上の空で、びくびくしている」
「そんなことないよ」
「そう、それならいいけど」
夏の校庭でメグミは日射しを浴びて自信たっぷりに歩いていた。まるで太陽の光はメグミ一人に向かって降り注いでいるかのようだった。メグミさん、きれい。フミはいつもながら感嘆した。
「さあ、部屋に戻って休みましょう。山本先生におこごと言われる前に」
寄宿舎の玄関前では山本先生が直立不動で立っていた。頭に鉢巻を巻いた袴姿で、手には薙刀を持っている。
「遅いわよ」
「先生、どうしたのですか、その恰好」
「シスターの服はやめたのですか」
山本先生は春のバザーで修道尼の服を購入した。大層気に入ったようで授業中にも身に着けていた。
「お遊びは終わりよ。今年の夏は、厳しく監督しますからね」
「うわ、それじゃ私、早めに帰省しよう」
「だめよ。外泊届の日付を守りなさい」
「はーい、山本先生、承知しました。フミさん、さ、早く行きましょう」
メグミは笑いながらフミの手をとって中へ入った。
メグミさんはいいなあ、山本先生と気軽にお話しできて。フミはうらやましく思った。私はあんな風に先生と話したりできない。今も私、先生ににらまれている気がした。気のせいかな、やっぱり気にしすぎかな。

週が明けるとメグミは横浜の実家へ帰省した。早く戻ってきてね、フミは心の中で思った。
「メグミさんは帰省したのですか」
「ひっ」
背後から急に話しかけられてフミは驚いた。
「はい、山本先生。今、発ちました」
「あなたも淋しくなるわね。困ったことあったら何でも相談しなさい」
「はい、山本先生。ありがとうございます」
フミは一礼すると急いで部屋へ戻った。ああ、びっくりした。でも先生、心配してくれた。よかった。やっぱり山本先生がいると心強い。
居残り
空が曇ってきて夕方から雨が降り出した。
フミは寄宿舎の食堂に一人座って窓から空を眺めていた。雨足はだんだん強まり、遠くで雷の音が聞こえていた。フミは憂鬱だった。普段なら雷の鳴る雨空を見上げると、何故かわくわくするのだが、今日は気がふさいでしまう。今年の夏、帰省しなかったのはフミだけだった。広い寄宿舎に生徒は私ただ一人。誰もいない食堂で誰かに見られているかのような不安に襲われる。
稲妻が走った。外の庭が光る。その時、フミは何かを見たような気がした。植込みの中から覗く暗い双眼のような何かを。
ベッドで眠ろうとしていたフミは物音で目が覚めた。ドアが少し開いて、その隙間から廊下の明かりがもれた。
「だれ?」
フミは起き上がってドアのほうへ歩いた。ドアはもう閉まっていた。
「変だな、今たしかドアが開いて」
フミは両手で自分の肩を抱いて身震いした。夏なのに寒かった。急いてベッドに戻り布団をかぶった。
寄宿舎廊下
「フミさん、ちょっとよろしいかしら」
夕食の時間になり食堂へ向かう廊下を歩いていたフミは後から声を掛けられた。山本先生が燭台を手にして廊下に立っていた。
「はい、山本先生。何でしょうか」
廊下の暗がりのなかで、山本先生の顔が燭台に照らされて浮かび上がっていた。
「私は毎晩、警備のために寄宿舎のなかをパトロールしています。フミさん、今日からは一緒に歩いてくれるかしら」
「えっ、一緒に?あの、どうして」
「一人じゃ見落としがあるかもしれないし、あなたも一人で退屈でしょう」
山本先生は有無を言わさない強い口調でフミを見下ろしながら言った。
「今日、消灯時間の前に食堂へ来てちょうだい」
「今日?今日からもう始めるのですか」
「なにか出来ない理由がありますか」
「いいえ、山本先生。大丈夫です」
その晩からフミは山本先生と一緒に寄宿舎の中を歩いた。
「何かおかしなことを見つけたらすぐに言うのですよ、ためらわずに」
「はい、山本先生。わかりました」
人気のない広い寄宿舎は静まり返っていた。山本先生の持つ蝋燭の灯りで二人の周囲だけが仄暗く照らされていた。二人の静かな足音が高い天井に小さく響いた。
フミは恐ろしさに身を縮めた。こんなことはやりたくない。毎晩のパトロールが苦痛で仕方なかった。
実家
サキは久しぶりの実家でくつろいだ。
お盆が近付いており花やお供物の買い出しに行った。仏壇を掃除したり、提灯に破れがないか確かめたり、ろうそくを多めに揃えたりと忙しく立ち回った。お盆の時期だけでなく、仏様のお世話をすることは幼いころからの日々の習慣だった。寄宿舎に入ってからは仏様に向かい合うことはほとんどなかったので、久々に実家の手伝いをすることは新鮮でより楽しく感じられた。
寄宿舎
お盆が終わり、メグミが寄宿舎へ戻ってきた。
「メグミさん、お帰りなさい」
フミは喜んで出迎えた。
「フミさん、元気そうでよかったわ。お土産があるから、あとで私の部屋へ来てちょうだい」
メグミがいると途端に場が華やいだ。メグミの明るさの前でフミはほっと一息ついた。不安で怯えていた気持ちが吹っ切れた。
フミはメグミに相談しようかと迷った小さな出来事を忘れることにした。夏休み前に街で見かけた腕に傷のある男。その男の怒ったような視線。夜半に開かれる部屋のドア。山本先生と歩く夜の寄宿舎。どれもくだらない出来事だ。メグミさんに言ったら笑われるだけだ。もう今日からは大丈夫。メグミさんが寄宿舎に戻ってきたんだもの。
しかしメグミとフミはすぐに驚きの知らせを受取った。
サキが車と接触して天祥堂医院に緊急入院したのだ。二人は山本先生に許可をもらって天祥堂へお見舞いに向かった。
天祥堂医院
「具合はどう。驚いたわ」
サキは骨折と打撲で2週間ほど入院治療が必要とのことだった。
「思ったより元気そうで良かった」
「隅田川へ散歩に出た時、よろめいて車にぶつかってしまったの。すごい人混みで押し出されてしまって」
「気をつけて。サキさんらしくない。普段しっかりしているのに」
「そうよ、サキさん。もし事故に遭ったのが私だったら、フミさんらしいって言われるに決まってる」
フミの言葉に3人は声を上げて笑った。
「夏休みいっぱいは入院になりそう。9月の新学期には退院したいな」
「あせらず、ゆっくりお休みなさい」
「うん。それに今、寄宿舎に戻っても、きっと楽しくないよ」
フミは言った後で、しまったという顔をした。
「どうして」
「ううん。なんでもない」
「フミさん、何かあったの」
メグミにごまかしは効かない。フミは俯いていた顔をあげてメグミを見た。
「たいしたことじゃないの、ただ・・」
「なあに。言ってみなさい」
「山本先生が・・毎晩、誘いに来るの。一緒に寄宿舎のパトロールをするようにって」
「パトロール?」
「なにそれ」
「フミさん、先生と一緒に夜の寄宿舎を歩いているの?」
「怪しい者はいないか、異変はないかって?」
サキとメグミは顔を見合わせて吹き出した。
「二人が歩いているところ想像すると可笑しい」
「山本先生は真面目な恐い顔をして」
「隣でフミさんはビクビク怯えながら、今にも逃げ出しそうにして?」
「何に怯えているの?山本先生に?」
「ばかね、暗闇とかお化けにビクビクよ」
サキとメグミはお腹をかかえて笑い出した。
「そうね、可笑しいよね」
フミもバツが悪そうに笑い出した。3人で大笑いした。なんだ、おもしろい。私、どうしてあんなに怯えていたんだろう。フミは大きな声で笑いながら、メグミさん、サキさん、ありがとう、と心の中でつぶやいた。
寄宿舎廊下
「フミさん、ちょっとよろしいかしら」
「はい、山本先生。何でしょうか」
夕食の時間が近付き食堂へ向かって歩いていたフミは後から声を掛けられた。
山本先生は燭台を手にして廊下に立っていた。フミはいやな予感がした。前にも廊下でこんな風に声を掛けられた。そして夜のパトロールに誘われたのだ。メグミが戻ってきてからフミは夜のパトロールはお役御免となった。ほかにも戻って来た生徒がいるのでその生徒達とパトロールをするとのことだった。
山本先生は応接室のドアを開けてフミを部屋へ招き入れた。フミは緊張した。
「この本を覚えているでしょう」
テーブルの上には『降霊会』とタイトルのついた洋書が載っていた。
「はい先生」
暗い部屋の中で山本先生の顔が蝋燭に照らされていた。
「降霊会をやります」
「はっ、あの、今、なんて」
「今夜、降霊会を行います。メグミさんと一緒に、夕食のあと応接室へきてちょうだい」
「降霊会って、あの、今夜?」
「メグミさんには先程、伝えました。ほかの人に言ってはいけません。私とメグミさんとフミさん、三人で行います」
フミは食事が喉を通らなかった。向かいに腰かけたメグミは平然と夕食を口に運んでいる。
「メグミさん、山本先生から聞いたでしょう」
「フミさん、山本先生は誰にも言ってはいけないとおっしゃっていたわ。ここで話すのはよしましょう」
「でも、メグミさん、承知したの?」
「承知も何も、山本先生がそう言うのだから、やるしかないでしょう」
「私、怖い。一体なぜ、そんなことを」
「山本先生に何かお考えがあるのでしょう。詮索しても仕方ないわ」
「断ってもいいかしら」
「無理よ。あきらめなさい。きっと何か私たちに手伝ってもらいたいことがあるのよ」
「メグミさん、よく平気でいられるわね」
「だって、ここで断ったら、先生、困ると思うわ。ちょっと余裕のない顔していたもの」
夕食を終えてメグミとフミは応接室へと向かった。
降霊会
テーブルの上には蝋燭とウイジャボードが置かれていた。蝋燭の灯りに照らされて3人の女性の顔が浮かび上がっている。恐怖に歪んだ幼い顔、好奇の目を輝かせた美しく整った顔、そして、苦難を刻んだかのような厳格な顔。
「それでは始めます」
3人の女性はボードの上の銀貨に指をかけた。
「これより降霊会を始めます。我らに力をお貸し下さる精霊たちよ。どうか我らを真実へお導きください。払えたまえ、清めたまえ、我らを導きたまえ」
霊をいざなう言葉が発せられた後、山本先生がボードへ問いかけた。
「ユカリさん、来ていますか。ユカリさん、あなたですか」
三人が触れていた銀貨が動いた。
(ハイ)
「きゃっ、う、うごいた」
フミは恐ろしさに思わず声を上げた。
「フミさん。手を離しちゃだめよ」
メグミが小声で注意する。
フミが落ち着いたのを見計らい、少し間を置いてから、山本先生が精霊らしき存在へ質問を始めた。
「ユカリさん。あなたは、今、どこにいるのですか」
銀貨がボードの上を迷うように動く。
(・・エ・・ノ、ナ、カ)
「エ・・・家の中ですか」
(ハイ)
「どこの家ですか」
銀貨はボードの上を行ったりきたりしていたかと思うと、急にすごい速さでグルグル回り出した。
(イ、イ、ン)
「どこの家ですか」
(イ、イ、エ)
三人は顔を見合わせた。
フミは布団にくるまって震えていた。
蝋燭を囲んだテーブル、勝手に動く銀貨。考えまいとしても頭のなかで今夜の場面が次から次へと浮かんでくる。そしてあのカーテン。厚いカーテンが微かに膨らんでいた。それは人の形をしていた。人間なのか異形のものなのか、それはもしかしたら応接室から抜け出して寄宿舎の廊下をさまよい歩いているのかもしれない。そしてそれは今にもフミの部屋をノックしてくるような気がして、フミは恐怖で大声をあげそうになった。